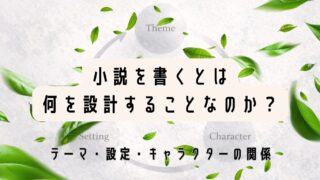 創作ラボ
創作ラボ 小説を書くとは何を設計することなのか?テーマ・設定・キャラクターの関係
小説を書くとき、テーマ・設定・キャラクターのどこから考えればいいのか迷うことがあります。本記事では三つの要素を「順番」ではなく「循環する関係」として整理し、創作の考え方の基準点を示します。
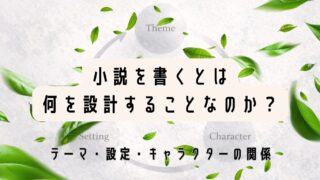 創作ラボ
創作ラボ  創作ラボ
創作ラボ  創作ラボ
創作ラボ -320x180.jpg) 創作ラボ
創作ラボ 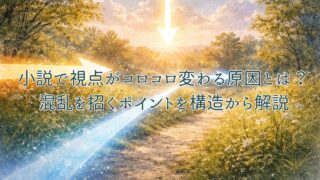 創作ラボ
創作ラボ 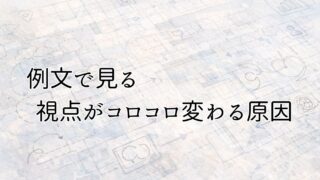 検証ラボ
検証ラボ -320x180.jpg) 検証ラボ
検証ラボ  創作ラボ
創作ラボ -320x180.jpg) 作品紹介
作品紹介  創作ラボ
創作ラボ